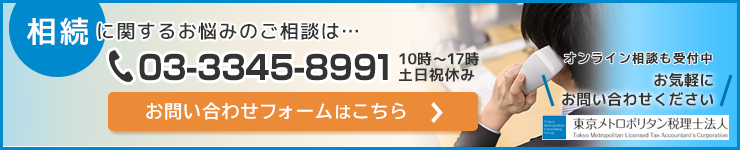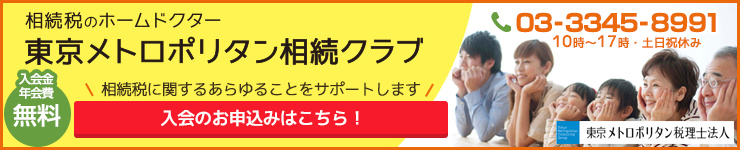実践!相続税対策
歩道状空地の相続税評価について【実践!相続税対策】第715号

2025.10.08
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
本日は、最近ご相談が増えている「歩道状空地の相続税評価」についてお話させていただければと思います。
まず、「歩道状空地」とは何かという点ですが、これは建築基準法において、建物の敷地内に設けられている一般に解放された通路部分をいいます。
具体的には、大規模なオフィスビルやタワーマンションなどで「通行のために提供された土地」で、建物の敷地としては使えないものの、所有権は残っている土地を指します。
この歩道状空地ですが、実は相続税評価において非常に注意が必要となってきます。
なぜなら、見た目は道路のようでも、法的には「私有地」であるため、相続財産の評価対象となることがあるためです。
では、どのように評価するのでしょうか。
国税庁の通達では、歩道状空地については特定の者の通行の用に供されているときは自用地評価額の100分の30に相当する価額によって評価することとなっています。
ただし、これは一律ではなく、その土地の位置、形状、通行状況などによって評価額がゼロとなるケースもあるため、個別の判断が必要となります。
具体的には、その歩道状空地が不特定多数の者の通行の用に供されており、下記の1から3に該当する場合は、相続税評価額がゼロとなります。
1.都市計画法所定の開発行為の許可を受けるために、地方公共団体の指導要綱等を踏まえた行政指導によって整備されたものであること
2. 道路に沿って、歩道としてインターロッキングなどの舗装が施されたものであること
3. 居住者等以外の第三者による自由な通行の用に供されている「歩道状空地」であること
なお、このような評価を行う場合は、開発登録簿や建築計画概要書、さらには分譲時のパンフレットなどで、歩道状空地であることを示す資料の提出が求められます。
これらが揃っていないと、通常の宅地もしくは私道と指摘されてしまう可能性もあるため、資料の収集や確認を慎重に行うことが肝要となります。
このように、歩道状空地は一見すると評価が不要に思える通路にあたりますが、実際には評価対象であり、かつ減額の余地があるという、非常に繊細な扱いが求められる土地です。
そのため、相続財産の中に「道路のような土地」が含まれている場合は、それが歩道状空地かどうかを確認し、適切な評価を行うことが重要です。
歩道状空地のような土地があるものの、判断がつかないようなことがあれば、ぜひ専門家にご相談いただければと思います。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
スーパーで「新米」の文字を見ると、高いと思いつつもつい手が伸びてしまう今日この頃です。
炊きたてのご飯に塩だけでも、十分なごちそうになりますし、秋は食卓が豊かになる季節ですね。
もれなく体重も豊かになってしまうため、食べすぎには気をつけようと思います。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html