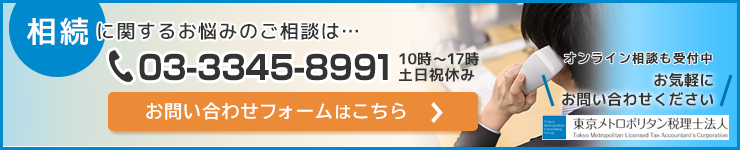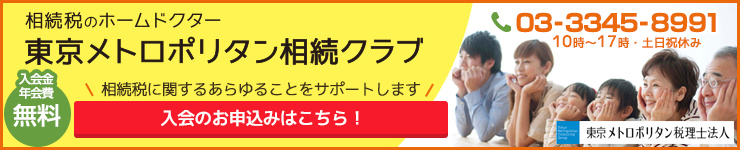実践!相続税対策
生命保険金の受取人と暦年贈与の注意点【実践!相続税対策】第708号

2025.08.20
おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
相続税を計算する際に、生命保険金には非課税枠があることは、ご存じの方が多いかと思います。
ただ、契約内容によって非課税でない場合もあります。それは、受取人を誰にしているか、です。
生命保険金については、500万円×法定相続人の数の非課税枠があります。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の合計3人の場合は、500万円×3人=1,500万円まで非課税となります。
ただし、受取人が法定相続人である場合に限ります。
上記の場合、配偶者が1,500万円の保険金の受取人となっていた場合は、1,500万円全額が非課税となりますが、受取人が相続人でない孫であった場合は、1,500万円の非課税枠は適用されません。
孫が受け取る1,500万円に対しては、相続税がかかってくることになります。
孫を生命保険金の受取人にしていた場合、別な不都合な問題が生じてくる可能性があります。
それは、相続税対策で、孫に生前贈与していた場合です。
孫に生前贈与をしていても、相続人でないため、通常は相続時に生前贈与額の相続財産への加算はありません。
(相続開始前3年から段階的に7年まで加算対象)
ただし、相続で財産を取得した場合(生命保険金も含む)は、孫も生前贈与加算の対象になってしまい、相続税対策が無意味になってしまいます。
さらに、孫の場合には、相続税額にその2割が加算される「2割加算」が適用されます。
孫に少しでも財産を遺したいと、孫を生命保険金の受取人とし、さらに生前贈与もしていると、思わぬ相続税がかかってくるため、要注意です。
《担当:税理士 宮田 雅世》
編集後記
生活資金に余裕がある方には、相続対策として生命保険の加入をおすすめしています。
生前、生命保険の加入手続きをしたにもかかわらず、途中解約されてしまう方もいらっしゃいます。
税率によっては、かなりの効果が得られますので、解約の際にはよく考えてから手続きしましょう。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html