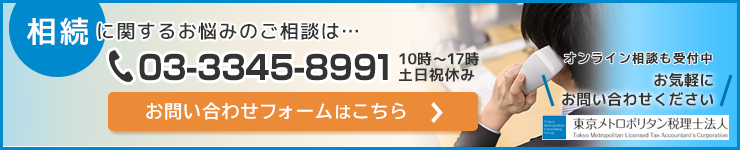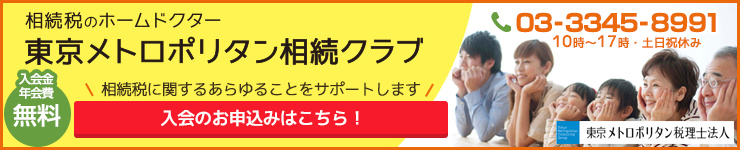実践!相続税対策
遺言書を作っておいた方が良い場合【実践!相続税対策】第714号

2025.10.01
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続税の申告や手続き業務に関わっていると、遺言書を作っておけば良かったのに、と思うことがよくあります。
たとえば次のようなケースです。
1.兄弟仲が良くなく、争いが生じそうな場合
2.相続人間の交流がなく、遺産分割がスムーズにいきそうもない場合
3.自宅不動産とか、同族会社の株式など、特定の財産を、特定の人に相続させたい場合
4.世話をしてくれた子に多く財産を相続させたい場合
5.子どもがいないため、配偶者と兄弟が相続人になるので、全財産を配偶者に相続させたい場合
6.離婚した配偶者との間に子がいて再婚した場合
7.親族以外の人に財産を渡したい場合
8.障害を持つ子がいる場合
9.出身学校や福祉団体などに遺贈寄附をしたい場合
等々
挙げてみると結構ありますね。
まずは、1、2のように、相続人間でうまく遺産分割ができないだろうというケースですね。
この場合には、遺留分(各相続人の最低限の取り分)に注意しながら遺言書を作ります。
遺留分は、子が相続人の場合は法定相続分の1/2です。
3、4の場合にも遺留分に注意しておく必要があります。
3の同族会社の株式などは、相続時精算課税や事業承継税制を使って、生前に贈与しておくという方法もあります。
自宅不動産については、生前に贈与してしまうと、小規模宅地特例が使えなくなりますので、これは相続での承継が良いでしょう。
5は是非やっておいて欲しいケースです。
配偶者と自分の兄弟が遺産分割協議をするのは、残された配偶者にとっては気が重いことです。
兄弟には遺留分がありませんので、遠慮なく配偶者に全財産を渡すことができます。
6の場合も、遺産分割協議がしづらいでしょうし、財産の額にも差を付けたいかも知れません。
再婚相手との間に子がいればなおさらです。
7以降は省かせていただきます。
以上、思い当たることがありましたら是非、遺言書を作成されてはいかがでしょうか。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
10月に入りました。そう言えばちょっと前までは、クールビズは9月までだったように思いますが、最近はまったく関係なくなってきましたね。
日本人も結構柔軟になってきたように思います。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html