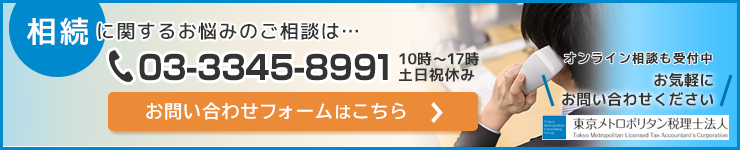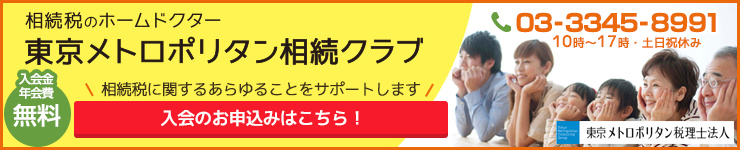実践!相続税対策
遺産分割協議時にわからなかった財産【実践!相続税対策】第707号

2025.08.13
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
相続が起こって、相続税申告をする際は、まずは亡くなられた方(被相続人)の財産を調査して、確定させることになります。
その上で、遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書では、どの財産を誰が相続するかを、相続人間で協議の上決めて、記載していきます。
その際、明確にわかった財産は具体的に記載していきますが、その時点はわからない、あるいは見つかっていない財産があるかも知れません。
たとえば、タンス預金(現金)であったり、貴金属類であったり、遅れて入ってきた還付金あったり、場合によっては、わからなかった少額の預金や株券などが出てくるかも知れません。
後々出てきた財産があった場合には、原則としてその財産についても、遺産分割協議をして誰が取得するのかを、決めなければなりません。
ほとんどの場合、後から出てくるものは細かなものが多いですので、いちいち遺産分割協議書を作成するのは、面倒です。
そこで、遺産分割協議書には、「本協議書に記載なき財産、または後日判明した財産については、相続人○○が取得する。」などと書いたりします。
同居していた配偶者が取得するなどと書くことが多いですね。
少額のものならそれで良いのですが、大きな財産が出てきた場合はどうでしょうか?
上記のように○○が取得する、と記載してあり、○○が取得すれば、それはそれで良いかと思います。
ただ、金額が大きいので、再度、相続人で話し合って遺産分割協議書を作成し、記載されていた○○とは違う人が取得した場合は、どうなのでしょうか?
場合によっては、遺産分割協議書に記載されていた○○から、実際に取得した人に贈与があったものとされてしまうと、贈与税がかかってきてしまいます。
ただ、遺産分割協議書の記載なき財産に関する記載は、あくまでそれに漏れてしまうような少額の財産を想定して書かれているものと考えられます。
したがって、高額の財産が出てきた場合には、再度遺産分割協議をすることは問題ないのではと、考えられます。
(それに類似した裁決事例での判断もあります)
したがって、遺産分割協議書には上記のような記載をするか、あるいは、どんな財産でも出てきた場合には、再度、遺産分割協議をするかを、明確に記載しておいた方が良いかと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
今週はあまり天気が良くなさそうですが、気温はあまり上がらないようで、その点は過ごしやすいかも知れませんね。夏休みの方も多いかと思いますが、どんな天気でも良い方に考えて、常に楽しい気分でいたいですね。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html