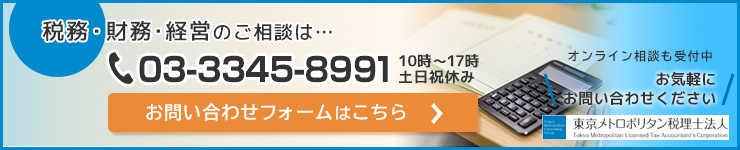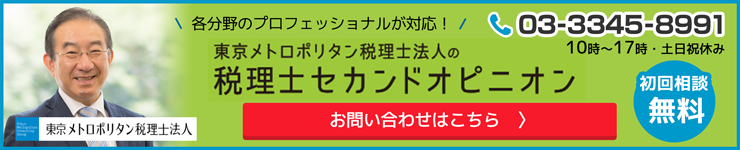実践!事業承継・自社株対策
事業承継税制を使うかどうか?【実践!事業承継・自社株対策】第261号

2025.08.07
Q:3年前に事業承継税制の特例承継計画を提出しており、計画には承継時期を書いたものの、いつのタイミングで事業承継をするか、悩んでいるところです。
また、この数年、業績が振るわなかったこともあり株価が下がっており、事業承継税制を使うのが良いのかどうかも悩んでいます。
どのように考えたらよいか、何かヒントをいただけるでしょうか?
A:事業承継の時期や事業承継税制の適用は、計画から実行まで、長い期間を要する場合もあります。
その間、景気や業界の環境、業績や内部の組織体制や社員の入れ替わり、自社の戦略の変更など、様々なことが起こってきます。
それにより、計画時とは大分様相が変わってくることもあります。
計画はあくまで計画ですから、実際の実行にあたっては、これを見直すことは当然のことですから、ご質問者の場合も、再度じっくり見直してみてはいかがでしょうか?
特例事業承継税制は、令和9年(2027年)12月末までに事業承継をする(先代経営者が代表を退任して、株式を贈与する)必要があります。
逆に言えば、それまで猶予がありますから、その間にどうするのか、じっくり考えることができます。
とは言え、社内的、対外的な対応もありますので、ギリギリというわけにはいきません。
2年ちょっとある今が、じっくり考える考え時ではないでしょうか。
特に事業承継税制を適用した場合は、その後の認定申請から贈与税の申告(第240号)、適用後の継続届(第255号)、取消事由への注意(第220号)など、様々な手続きや注意点があります。
また、一旦事業承継税制を適用すると、その納税猶予を継続するために、代々手続きを継続していく必要があります。
なかなか大変な負担を背負っていくことになります。
このようなことも考えると、事業承継税制を適用しない方法というのも、実際に実行する前には、考えておいた方が良いと思います。
たとえば、株価が下がっているのであれば、相続時精算課税を使って、株式を一括贈与してしまうことも考えられます。もちろん、事業承継税制を使わずに、です。
この場合の贈与税はいくらか、将来相続が起こったときにはどのくらい相続税の負担になるのか、株価は最も高いときからどのくらい下がっているのか、などなどいろいろ検討してみてはいかがでしょうか?
事業承継税制を使わず、相続時精算課税で贈与した場合は、その時には贈与税負担が生じますが、株式は一気に移動でき、将来の煩わしい手続きは必要なくなります。
このメリットも非常に大きいのかと思います。
納税猶予を使うか、使わないか、特例承継計画を出してあれば、どちらも選択することができます。
残された期間は長くはありませんので、この時期にじっくり考えてみることをお奨めします。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
8月も中盤に差し掛かり、夏休みモードになってきた感がありますね。
皆様はどのような夏休みを過ごされますでしょうか?
連日の猛暑が続いていますので、是非、無理のないようゆったりとした夏休みにしたいですね。
メルマガ【実践!事業承継・自社株対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001685356.html