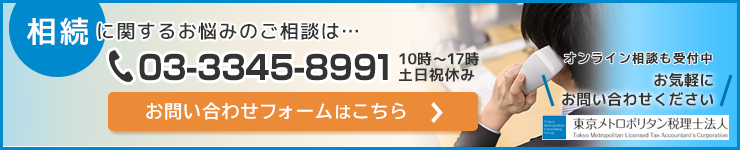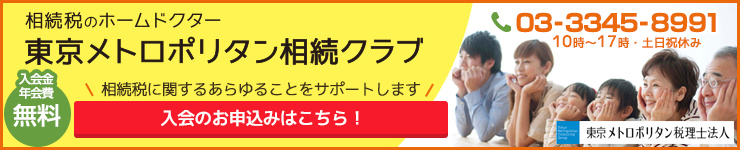実践!相続税対策
相続時精算課税の基礎控除内申告【実践!相続税対策】第694号

2025.05.14
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
令和6年より、相続時精算課税にも基礎控除年110万円の枠ができたことは、ご存じの方も多いかと思います。
相続時精算課税とは、60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫が贈与を受けた場合、通常の暦年課税との選択により、適用を受けられる制度です。
内容としては、贈与時には2,500万円まで贈与税をかけない代わりに、贈与した人が亡くなったときには、その贈与した財産を相続財産に加算して、相続税で税金を精算する、という制度です。
この2,500万円の非課税枠(特別控除)は、相続時精算課税を選択したときから、累計で控除していきます。
贈与額が2,500万円を超えた場合は、超えた金額の20%の贈与税を支払うことになります。
この支払った贈与税は、相続時には相続税から控除することができます。文字どおり相続時に精算する課税方式ということです。
さて、令和6年から相続時精算課税にも基礎控除110万円ができたということを、冒頭にお話ししました。
この110万円は、2,500万円の特別控除とは別に設けられたもので、年110万円までの贈与であれば、申告する必要もなく、2,500万円までの累計計算にも含まれない、ということになります。
したがって、毎年110万円以内の贈与であれば、相続時に相続財産に加算して、精算する必要もありません。
したがって、相続時精算課税を選択した上で、毎年110万円の贈与を行っていく、という相続税対策も考えられます。(実際に行っている方も多くなってきました)
通常の暦年課税で贈与すると、110万円まで贈与税がかからないのは同じですが、相続開始前7年間にした贈与は、相続財産に加算されることになっています。(生前贈与加算)
これも以前は相続開始前3年間でしたが、令和6年からは、7年間に延長されています。(加算期間は徐々に延長されていき、令和13年の相続からフルに7年間加算になります)
まさに、暦年課税を使うよりは、相続時精算課税を使った方がいいですよと、国が言っているようなものです。
そこには、相続時精算課税を標準にして、贈与税と相続税の一体課税に移行していきたい、という思惑もあるものと考えます。
では、相続時精算課税を選択して、基礎控除の110万円以内の贈与をした場合は、申告をしなくてもよいのか、ということですが、これはしなくても構いません。
相続時精算課税を選択する初年度に、「相続時精算課税選択届出書」を出しておけば、110万円以内の贈与の場合は、贈与税の申告を出す必要はありません。
注意すべきは、110万円以内だからと、上記選択届の提出を3月15日までにするのを忘れてしまった場合です。
この場合には、相続時精算課税を選択したことにはならず、暦年課税となります。届出が出てないので致し方ないですね。(ただし、110万円以内なので、いずれにしても贈与税はかかりませんが)
もう一点、注意すべき事項が本日の主題です。(ようやく辿り着きました)
それは、相続時精算課税を選択して、110万円以内だからということで、申告をしない場合です。
これはこれで良いのですが、その後に実は110万円以上贈与をしていた、あるいは贈与した財産の評価を間違えて、実は110万円以上だった、というような場合です。
この場合何が問題かというと、特別控除2,500万円の控除ができない、ということです。
2,500万円の特別控除を受けるには、期限内(3月15日)までに申告をしていることが要件となっています。
したがって、期限後に申告した贈与額が間違っていることに気づいた場合において、期限内に申告をしていなかった場合は、2,500万円を控除することができません。
たとえば、110万円の贈与だったつもりが、他に贈与していたのを失念して200万円の贈与だった場合、基礎控除を90万円オーバーしてしまっています。
このオーバーした90万円については、2,500万円の控除残額があっても引くことはできず、20%の18万円の贈与税支払うことになってしまいます。
したがって、贈与の失念や、評価の間違いなどがある可能性も考えて、110万円以内の贈与であっても申告をしておいた方が良いのではないかと思います。
以上、相続時精算課税を使うときには、是非、注意していただければと思います。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
5月も中旬、暑くもなく(多少暑いかも知れませんが)、寒くもなくいい季節ですね!
こういう季節が昨今は長続きせず、急速に暑くなってきますので是非、この時期を行楽等いろいろ楽しんでいきたいですね。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html