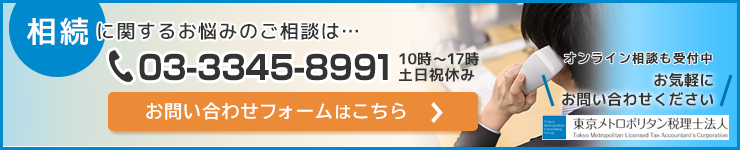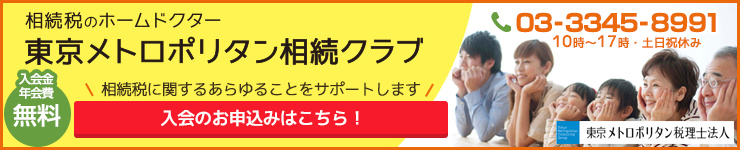実践!相続税対策
相続税の障害者控除とは【実践!相続税対策】第720号

2025.11.12
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
本日は、相続税申告において見落とされがちな「障害者控除」についてお話させていただきます。
まず、相続税の「障害者控除」とは何かという点ですが、これは相続人が一定の障害者に該当する場合に、相続税額から一定額を控除できる制度をいいます。
この制度は、障害者の生活保障の観点から設けられており、税負担の軽減を図ることが目的とされています。
では、どのような人が障害者控除を受けられるかというと、障害を持たれている相続人が下記の3つの要件すべてに当てはまっていなければなりません。
・財産の取得時に日本国内に住所があること
・財産の取得時に障害者であること
・財産を取得した人が法定相続人であること
なお、障害者であることの判定については、被相続人が亡くなり、相続が発生したときに障害を持っているか否かで判断することになります。
そのため、相続開始前に障害を持たれていても、その後回復された場合は対象から外れてしまいますので、この点は留意するようにしましょう。
次に、障害者控除額を算定する場合ですが、相続人が「一般障害者」と「特別障害者」のどちらの区分に該当するかによって計算式が異なってきます。
この、「一般障害者」とは常時の介護を必要としない比較的軽度から中程度の障害を持つ方で、障害者手帳の種類や等級に基づき、以下に該当する方を指します。
・身体障害者手帳:3級、4級、5級、6級
・精神障害者保健福祉手帳:2級、3級
また、「特別障害者」とは重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある以下に該当する方を指します。
・身体障害者手帳:1級、2級
・精神障害者保健福祉手帳:1級
最後に控除額についてですが、
一般障害者の場合は、「85歳までの年数×10万円」
特別障害者の場合は、「85歳までの年数×20万円」
となります。
たとえば、40歳の障害者が相続人であれば、
45年(85歳-40歳)×10万円=450万円
の控除が可能となります。
同じ条件で、特別障害者が相続人であれば、
45年(85歳-40歳)×20万円=900万円
の控除が可能となります。
なお、この85歳になるまでの年数は、85歳から相続開始時の満年齢を差し引いてカウントします。
たとえば、相続が発生した時点で、40歳10ヶ月であった場合には「40」とカウントすることになります。
障害者控除を適用するためには、障害者であることを証明する書類の提出が必要となってきます。
具体的には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または医師の診断書などが該当しますので、こうした書類はすぐに提出できるよう準備しておくことが肝要となります。
障害者控除については、実務上、申告漏れが起こりやすい項目の一つです。
特に、障害の程度や年齢の確認が不十分なまま、申告が進められてしまうケースがよく見受けられます。
そのため、相続人の中に障害者がいる場合は、早めの資料収集と確認を行うことが大切です。
また、障害者控除は、配偶者控除や未成年者控除など、他の控除制度と併用することも可能です。
これらを組み合わせることで、相続税の負担を大きく軽減することができます。
障害者控除が適用できそうかどうか分かりかねている場合は、専門家へのご相談をお勧めいたします。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
気づいたら11月も半ばを迎えており、今年は秋の味覚を食べ損ねた気がしています。
残念ではありますが、12月になるとおでんや鍋といった温かい食べ物が美味しくなるので、そうしたものでお腹を満たそうと思います。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html