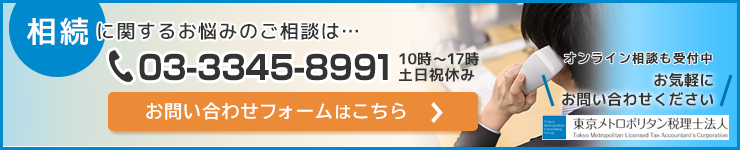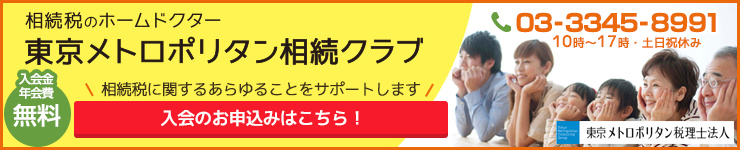実践!相続税対策
最近聞くようになった配偶者居住権ってなに?【実践!相続税対策】第695号

2025.05.21
皆様、おはようございます。
資産税部の太田遼です。
突然ですが、皆さまは配偶者居住権といった権利を聞い
たことがありますでしょうか。
この権利ですが、2020年4月1日以降の相続から設定された権利でして、名称のとおり、配偶者のための権利となっております。
特にご高齢の配偶者を守るために作られた権利でして、
「夫が亡くなったあと、私はこの家に住み続けられるの?」
といったような不安を解消するためにできました。
この権利の内容を知っておけば、相続人同士のトラブルを避けられることもあるので、どういったものなのか早速お伝えしていこうと思います。
まず、この権利ですが、残された配偶者が亡くなった夫または妻の家に住み続けられる権利、とご理解ください。
そう聞くと、自宅に住み続けられる権利をわざわざ設定する必要はあるのか?と、疑問を感じる方もいらっしゃるかと思います。
そこで、一つ具体例を用いて、この権利が設定される前の問題点をみていきましょう。
<具体例>
・相続財産:自宅(3,000万円)と預金(3,000万円)
・相続人:妻(75歳)と娘(40歳)
・相続割合は、妻と娘で半分ずつ(3,000万円ずつ)
この場合、妻が「家に住み続けたい」と思っても、家の価値が3,000万円なので、それだけで相続分を使い切ってしまうことになります。
そのため、妻は自宅だけを相続し、娘は預金の3,000万円を相続することとなり、老後の生活資金を相続することができなくなってしまいます。
これではいけないということで設定されたのが配偶者居住権です。
この権利ができたおかげで、上記のような相続であっても、配偶者は自宅に住み続けられる「家に住む権利」と預金の一部を相続できるようになったのです。
先ほどの例でいえば、自宅3,000万円はたとえば、配偶者居住権1,500万円と、所有権1,500万円のように、分けることができるようになるのです。
こうすれば、妻は配偶者居住権(1,500万円)と 預金1,500万円を相続でき、娘は家の所有権(1,500万円)と預金1,500万円を相続することができます。
※詳細に計算をするとなると、評価額は半分ずつにはなりませんが、今回は分かりやすくご説明するため妻と娘で半分ずつとなるようにしております。
こうした遺産分割ができれば、将来の生活費を確保しつつ、自宅にも住み続けられ、平等な相続分で他の相続人とトラブルになることも避けられます。
「家に住み続けたいけど、生活のためのお金が心配…」
そんな声に応える制度が、配偶者居住権です。
相続は「争族」にならないよう、早めの準備と知識がカギとなってきます。
次回はそんな配偶者居住権に小規模宅地等の特例が適用できるのかどうか解説しますので、是非、またお読みいただければと思います。
こういった制度を適用したほうがいいのか気になる方は、ぜひ専門家に相談してみてくださいね。
《担当:資産税部 太田 遼》
編集後記
気づけば5月も終わりが近づき、今年ももう5ヵ月経ってしまったのかと驚くばかりです。
税理士受験生である私は、本試験の8月が近くなってきたことに若干の焦りを感じております。
まもなく梅雨に突入するこの時期、体調を崩さぬよう好きなラーメンでも食べて、ラストスパートに向けて頑張ろうと思います!
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html