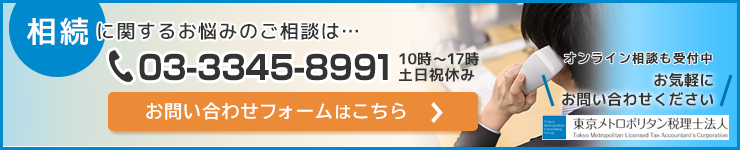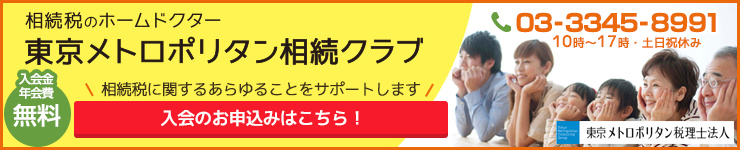不動産 税金相談室
庭内神しって相続税評価額に影響するの?【不動産・税金相談室】

2025.10.21
Q 私の自宅の庭には、祖父の代から大切にしている小さな祠があります。石で囲まれたスペースに、木製の小さな社(やしろ)が設置されており、家族で定期的にお供えをしたり、お参りをしています。
昔から「神様がいる場所だから大事にしなさい」と言われてきたので、建物を建てたり物を置いたりすることは避けてきました。
最近、相続のことを考えるようになり、自宅の土地の評価額を調べているのですが、この祠のある部分も他の土地と同じように評価することとなるのでしょうか?
それとも、何か特別な評価をすることとなるのでしょうか?
A ご自宅の庭にある祠についてですが、これは税務上「庭内神し(ていないしんし)」と呼ばれるものに該当する可能性があります。
庭内神しとは、個人の信仰に基づいて敷地内に設けられた小さな社や祠のことで、祖先崇拝や地域の風習に基づいて代々受け継がれているものが多いです。
このような庭内神しがある土地については、相続税の評価において特別な取り扱いが認められています。
というのも、庭内神しが設置されている部分は、信仰の対象として日常的に供物を供えたり、お参りをしたりしているため、実質的に宅地としての利用が制限されていると考えられるからです。
たとえば、その部分に建物を建てたり、駐車場として使ったりすることは、心理的にも現実的にも難しいと判断されることが多いものです。
そのため、相続税評価においては、庭内神しが設置されている部分の土地について、「墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」として相続税の非課税財産として法的に認められると考えられます。
ただし、国税庁の「『庭内神し』の敷地等に係る相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の取扱いの変更
について」では、庭内神しの敷地として認める条件として、以下の3つのポイントを挙げています。
1.庭内神しの設備が信仰の場として敷地に定着しており、外形も境内地等の様相を成していること
2.庭内神し及びその附属設備が建てられた経緯や目的が日常礼拝に沿っていること
3.庭内神し及びその附属設備が、礼拝の場として機能していること
また、税務署に対してその状況を説明できるよう、現地の写真や図面、供物の状況などを資料として準備しておくことが肝要です。
ご相談の内容からすると、祖父の代から大切にされてきた祠があり、日常的にお参りもされているとのことですので、非課税財産として認められる可能性は十分にあると思われます。
相続税の申告にあたっては、こうした部分も見落とさずに評価を行うことで、適正な税額を算出することができますので、ぜひ一度、専門家に現地を見てもらいながら評価の方法を検討されることをお勧めします。
≪担当:資産税部 太田 遼≫
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html