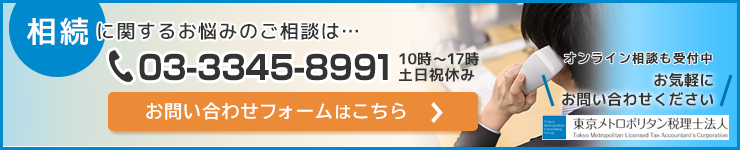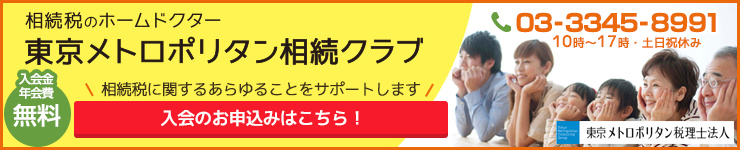実践!相続税対策
自筆証書遺言書の保管制度の利用【実践!相続税対策】第711号

2025.09.10
おはようございます。
税理士の北岡修一です。
自筆証書遺言の保管制度があるのは、ご存知でしょうか?
遺言を書く際は、大きく分けると、自筆証書遺言か公正証書の2つがあります。
財産が多く、複雑な遺言を書く場合は、公正証書遺言にしておいた方が確実です。
ただし、手間とお金がかかります。
それほど財産が多くなく、シンプルな内容の遺言であれば自筆で書くことも考えられます。
この場合の懸念点は、遺言の形式に不備があって無効になってしまう可能性もある、ということです。
また、せっかく書いた遺言がどこにしまってあるかわからず、遺族に発見されなかったり、紛失したり、場合によっては改ざんなどが行われてしまう可能性もあります。
そこで、自筆証書遺言を確実に実行できるように、平成30年の民法改正により「自筆証書遺言書の保管制度」が創設されました。
この制度を利用することにより、自筆証書遺言書が法務局で適正に管理保管され、遺言を確実に実行することができます。
この保管制度を利用することにより、
1.民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、保管申請時に外形的チェックが受けられます。
2.遺言書は、原本に加え画像データとしても長期間適正に管理されます。これにより、遺言書の紛失、改ざん等を防ぐことができます。
3.遺言者が亡くなったときは、相続人は法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書(公的手続きに使える書類)の交付が受けられます。
4.遺言者が亡くなったとき、自筆証書遺言書では通常必要な家庭裁判所における検認が不要となります。
などのメリットがあります。
具体的な書き方は以下のとおりです。
1.遺言書の全文、遺言の作成日付および遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
2.財産目録は、自書でなくパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や、通帳のコピー等の資料を添付する方法でも構いません。ただし、この場合は全ページに署名押印をします。
3.用紙はA4で片面のみ使用します。また、各ページにページ番号/総ページを記載し、余白の要件もあります(自筆証書遺言書保管制度サイトで確認)。
同サイトに専用用紙がありますので、ダウンロードして使うと良いかと思います。
以上により、遺言書を作成したら、保管を行う法務局に予約の上、訪問することになります。
法務局では、スキャナで遺言書を読み取るため、すべてのページをバラバラのまま提出することになります。
保管をする法務局(出張所)は、どこでもいいというわけではなく、東京都の場合は、次の場所が指定されています。
本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局
保管の申請には、遺言書や申請書のほか、本籍地記載のある住民票、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証)が必要となります。
また、保管手数料は、遺言書1通につき3,900円です。公正証書遺言よりもずい分安い費用でできますね。
保管の申請が終われば、保管証が交付されます。
この保管証があれば、遺言書の閲覧、保管の撤回、変更の届出をするときに便利です。
また、相続人等が遺言書情報証明書などの交付の請求するときにも使えますので、大切に保管してください。
以上、遺言書を作成する場合には、この保管制度の活用も是非、検討してみてください。
《担当:税理士 北岡 修一》
編集後記
高齢になってくると自筆で遺言書を作成するのも大変になってきますね。上記保管制度によれば、遺言の変更や撤回も行うことができますので、早めに作っておくと良いかと思います。
また、保管証は家族の方にも保管場所を知らせておくことで相続の手続きをスムーズに行うことができるのではないでしょうか。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html